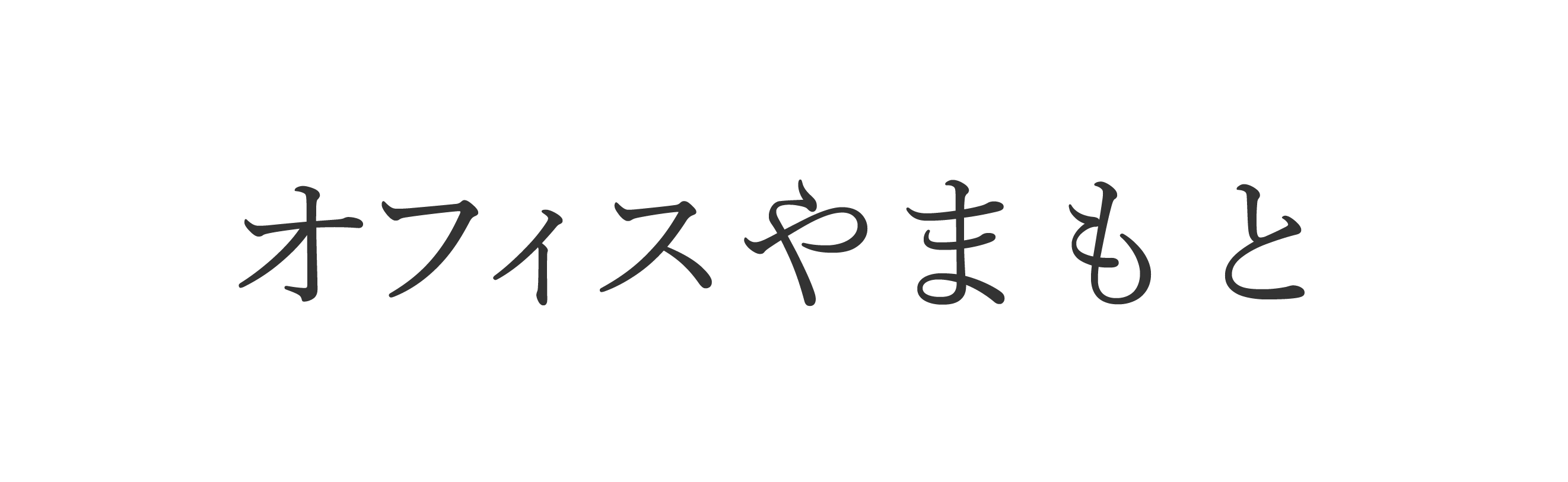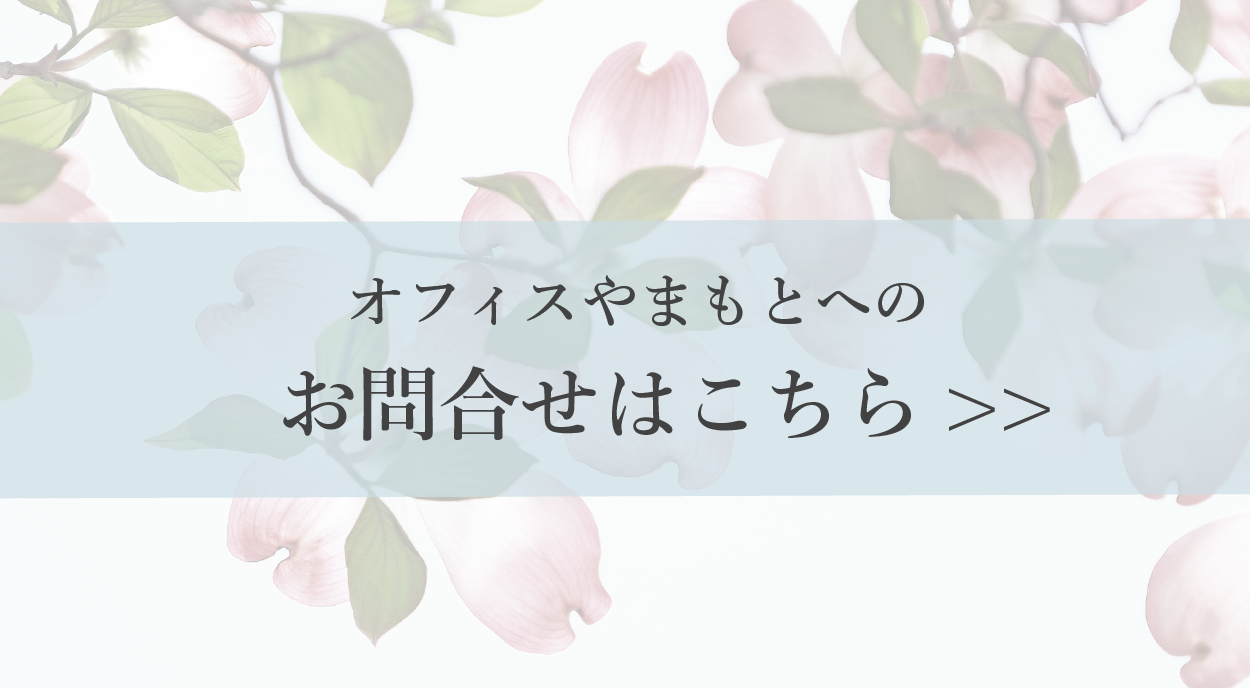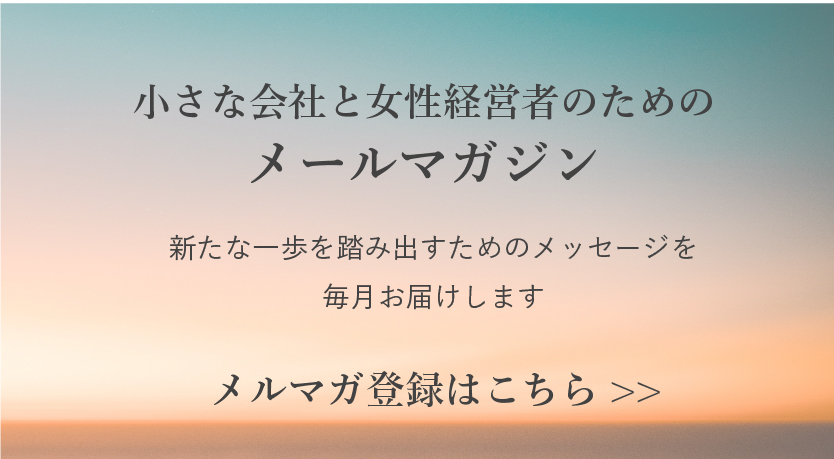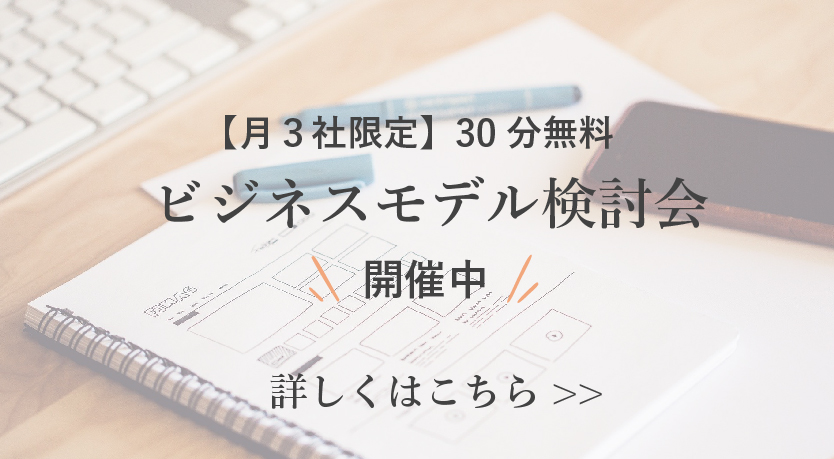いわゆる明治の良家の上品な女性の行き方を礼賛するような本では無くて、
どんな環境にあっても自分の尊厳は自分で守り抜く女性の生き方のお話しです。
武家出身の明治12年産まれの著者の祖母は11歳の時、家計を助けるため子守を請け負い、
石飛でけつまづき躓き背中に背負った幼い子に怪我させまいと転んだ時に背中の子を両手で押さえ
手をつかず、左目から地面に落ち左目を失明してしまいます。
自分だって相当な激痛だったでしょうに、転んでも直ぐ立ち上がり、預かっていた子を危ない目に合わせた
と謝ったと言います。
その両親も、左目を失明した娘を「かわいそう」とは扱わず、
父親は「天から心眼を与えられた。左目を失っても生きてゆくという運命を与えられたということは
それぐらいの心の強さ見込まれているのだろう」と言われ決して娘を「かわいそう」「不憫」とは
扱わなかったそうです。
眼が不自由なだけではなく、現代と違い整形外科などない時代、怪我の傷跡は思春期を前にした
少女には相当堪えたことでしょう。
その後親の決めた縁談で商家のあそび人の長男に嫁ぎ、まもなく婚家は没落。
それでも誰を恨むことなく、家に居つかない夫を責めず、愚痴らず、誇りをもって
運命を受け入れその重たさを自分で受け取りながら前に進まれます。
何カ月も夫が家を空け、居所を探し当て家に入ったら、見知らぬ女性とその母親までもが
同居していたこともあったあったそうです。
関東大震災や第一次世界大戦、第二次世界大戦と激動の日々と激動の家庭にあって
淡々と平常心でばかりいられたとはとても思えない日々を、
「私だけが不孝」にも「私だけが頑張っている」にも陥らず
自分の力も活かし、人の力も活かし、周りに灯りをともすように生き方がここにあります。
自然からも世界からもこれまで聞こえなかった、足音が聞こえる今の世にこそ
一読頂きたい一冊です。