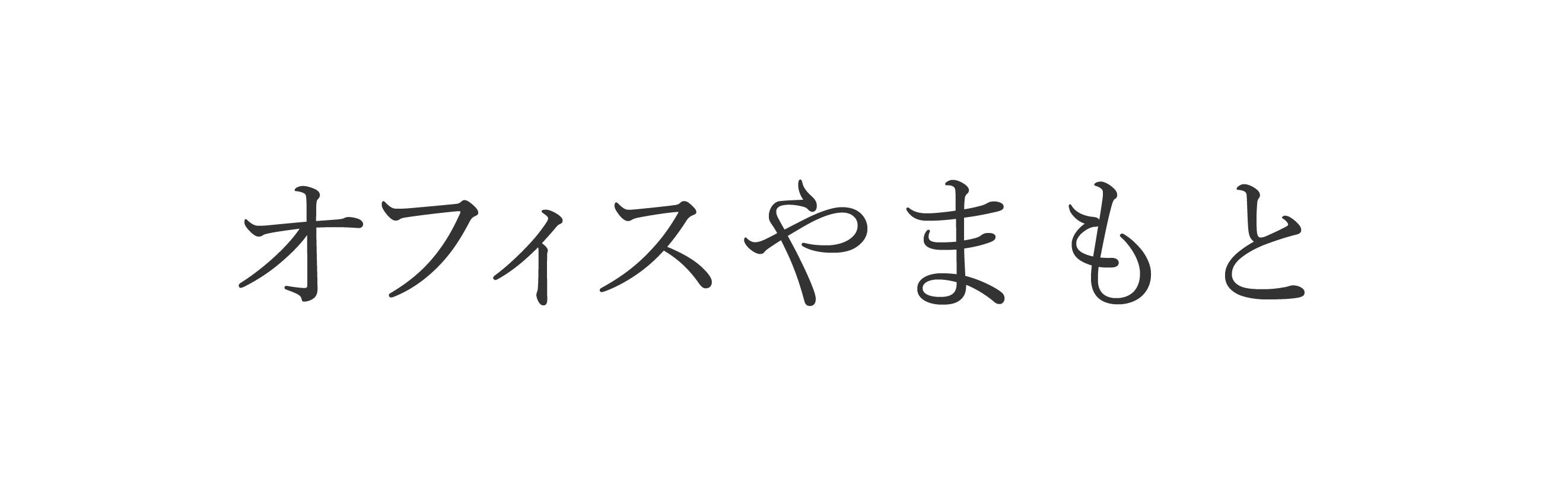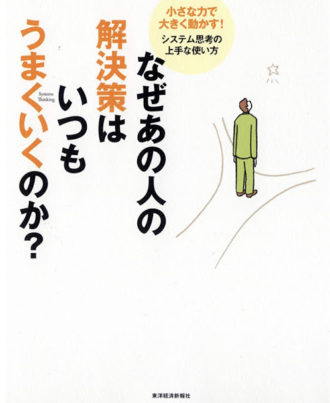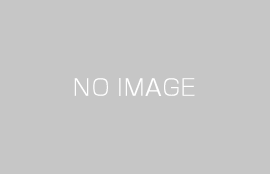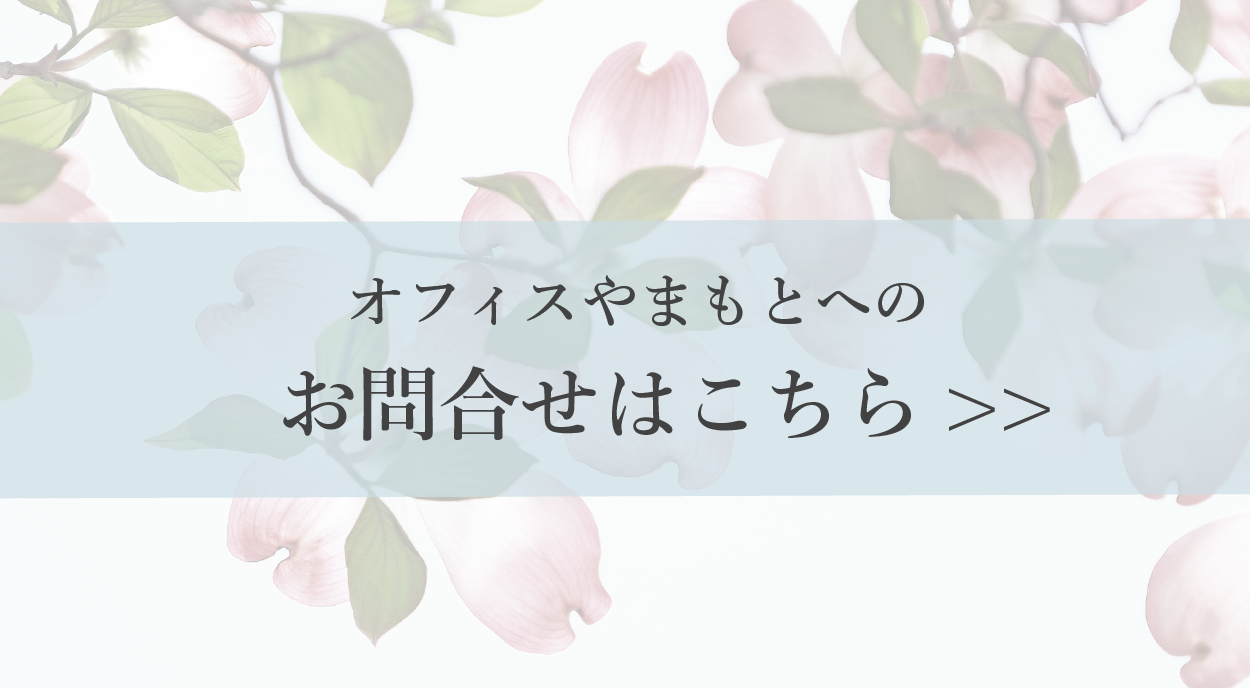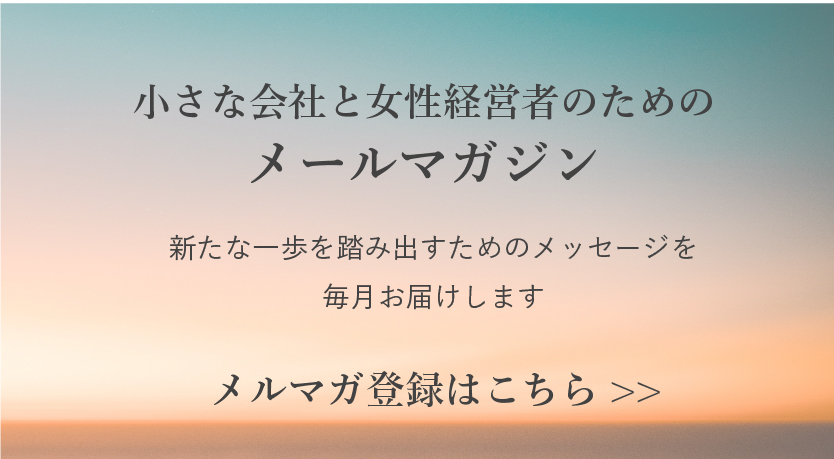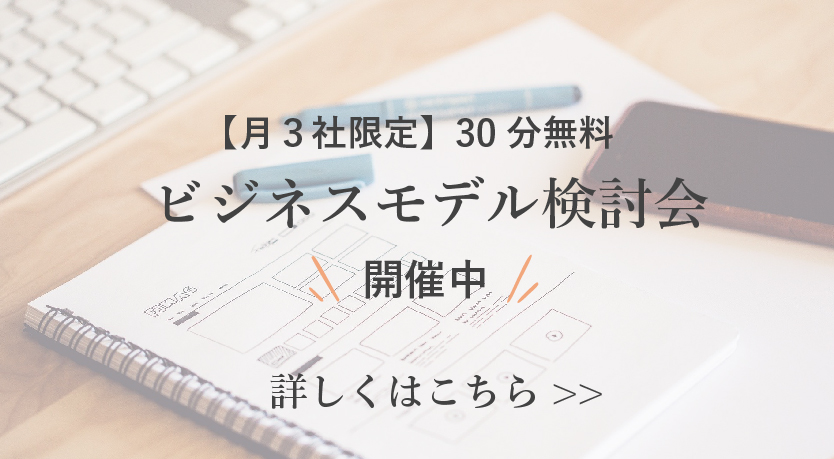経営と会計をきりはなして考えることは出来ません。
この至極当然なことが、ときどき忘れられます。
「帳簿の世界史」(文藝春秋社 刊 著 ジェイコブ・ソール)によれば、
企業だけではなく、国家も会計と向き合うこと無くして繁栄はないことを歴史が教えてくれます。
あのルイ十四世は、家臣に会計帳簿を付けさせ、年に二回
自分の収入、支出、資産が記入された新しい帳簿を受け取り自分の王国の決算を確認していました。
けれど、財務総監を務めていた男が亡くなるとすぐその習慣を辞めてしまいました。
赤字続きだった自国の財政状態を知ることは、統治者としての自分の
失敗をあからさまに示す不快な代物になっていたのでしょう。
よい会計は、悪いことがおきたときに真実を教えてくれます。
朕は国家なりと言いきった王様に真実を告げる家臣はなく、
彼は死の床で、自分はフランスを破綻させたと告白したそうです。
ルネッサンス期のフィレンツェを支配したとまで言われるメディチ家は
わずか一代で失われてしまいました。なぜでしょう。
代々銀行家で地味な会計の習慣を引き継いできた一族が、ヨーロッパ一の富豪となり
繁栄したとき、当時の当主コモジがその息子達に会計を学ばせなかったのです。
コモジの息子達は豊かな教養は身につけ、芸術を理解し、政治はできても会計ができず、
銀行業の実務を任せるものがいても監査機能を果たすことが出来なくなったのです。
ルイ十四世のエピソード、メディチ家のエピソードどちらも、歴史上の出来事と言えない
ぐらいリアルに感じるのは私だけでしょうか?
会計に暗い企業に繁栄無く、会計に明るい企業に没落はない。
会計と経営を切り離して考えることが出来ないのはごくごシンプルな原則です。